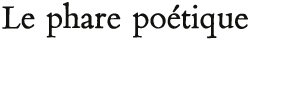

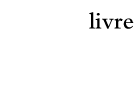
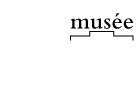
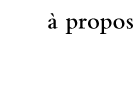
白井明大
白梅へ雲の林のかかりたる
宮本佳世乃の第一句集『鳥飛ぶ仕組み』でもっとも好きな句です。目の焦点は白梅とその背後を行き来して、遠くの雲が、向こうの林が、花にかかっていると私は読みます。〈雲の林〉をひとまとまりにも解せますが、むしろそれぞれ、雲がかかり、林がかかる、そのような白梅のさまの遠近感がぶれそうな小ささに何度もピントを合わせようと目を凝らすようにしてこの句を読むのが好きです。
そして、己を空しくして白梅に眺め入る書き手のけはいのなさに気づかされます。事物事象のさまを言い指す語の一つ一つから抒情を捨象し、書き手自身の存在を背後に退かせて、事物を主、己を従として句作する宮本の姿は、私が子規や青畝らの句に感じ、受け取ってきた写生句のありようを現代に引き継ぐものに思われます。己を空しくするとは、生の実感の希薄さや個性の乏しさなどではなく、写生に際して対象と向き合う姿勢の一ですが、自己を表出せんとするところから遠くあるその姿勢をとる者は、現代の書き手において稀有といえます。
第二句集『三〇一号室』では、前句集からさらに深まりを得た句の姿をひしと受け取りながら読みました。
みづうみのひらくひばりのなかに空
何かをくぐり抜けた後に、心の自由さを得られたような、読んでいるこちらまで軽やかさを伴う内面の広がりを覚えるような、そのような句に感じます。〈みづうみ〉により〈ひら〉かれた光景としての〈ひばり〉のさま。抽象度の高い視覚的イメージに、〈ひら〉と〈ひば〉の〔h〕ではじまり〔イ音+ア音〕から成る音の反復が合わさって句がぐんと展開します。〈ひら〉いたイメージに満ちた〈ひばりのなかに〉、そうか、〈空〉があるのか、とこの句を受けとったとき、〈空〉とは「そら」であり「くう」でもあり、とらえどころの何もない無限さに包まれました。〈ひら〉かれる感覚を伴い現われた〈みづうみ〉、〈ひばり〉を宮本は見つめ、その末に見出した〈空〉の奥行きを思います。
この句は事物事象を写しとる写生に留まらず、事物に心象を重ねる詩法を採ります。いわば事物が従、己が主の句ともとれます。それでいてやはり、己を空しくする宮本の句の世界を感じもします。なぜなら句の中に事物の叙述から離れて心象を表わす語がなく、あくまで眼に映るものに沿う姿勢が保たれているからです。〈ひばりのなかに空〉を見る眼のふしぎを思います。そこに、己を空しくして句をなす宮本のさらなる変化と深まりを見ます。ただ、この句集に現われる〈空〉は一様ではありません。
星月夜ひとり喫煙ひとりは空
夜に点る光。〈ひとり〉は〈喫煙〉の火を点し、もう〈ひとり〉は〈空〉に光るという情景です。機上の人か、あるいは天にいるのでしょうか。後者と読むとき、故人へのまなざしが句に窺われます。空は心の比喩となるのと同じくらい死の比喩ともなります。この句集に表わされる〈空〉には、冒頭の〈来る勿れ露草は空映したる〉のような微細な客観叙述(草露に映る光景と解して)から、〈うづくまる空に泰山木の花〉のような心象の表出、〈一面のコスモス空へ還りたる〉に見られる死の暗喩、〈末黒野と菜の花の空隣り合ふ〉のような複数の〈空〉のイメージの呈示まで多様です。この句集で多様なイメージの〈空〉は、私のなかに折り重なり、次第にひとつになっていきました。
宮本は、第二句集へと至る句作と、こうして一冊に編んだ時間のどこかで、心の自由さを得たのではないだろうかと一読以来、私は感じています。悲しみは悲しみとしてありながら、それが時に〈みづうみへきしんだゆきをすてにけり〉や〈菜の花の深いところを蹲る〉など、読むこちらがひしと感じるほどに表わされながら、同時に自由でもある、そうした心境に至りつく句の歩行があるように読みました。集中の句を順を追い〈みづうみの〉の句に行きつく流れにあると解せるものを引いていきます。
十月のひかりの橋を渡りけり
〈ひかり〉を見たこの句は、静かです。〈渡りけり〉と、たしかに宮本はどこかを渡り越えます。
秋の川扉ちらちら開きをり
〈開き〉という語が現われます。まだ予兆かもしれません。〈扉ちらちら開〉の〔イ音+ら〕の反復と合わさって、微かながら何かが開かれる兆しは告げられます。〈手鏡にうつるくちびる小鳥くる〉の〔る〕のくり返しも印象的ですが、軽やかな音韻に向日性のサインがちりばめられます。
崖線をゆくぽろつとぽろつとゆく
ここに句集の最初の高まりを見ます。〈橋を渡〉った後、崖線を危うげに、それでも〈ゆく〉姿に打たれます。〈ぽろつとぽろつと〉の反復は〈秋の川〉や〈手鏡に〉の句の音の軽やかさと違い、悲しみや脆さを帯びています。だからこそ〈ゆく〉の意志を深く受け取ります。
凍てた木のとほくに舟を洗ふ人
これはどんな眼の働きでしょう。写実であろうこの句に、〈とほく〉とはこの世の距離ではないようにも思わされます。〈凍てた〉、〈洗ふ〉の二語に冷たく澄んだ世界を感じるゆえでしょうか。宮本の眼は死の〈とほく〉をも見つめうるかのようです。生と死に視線を往来させる眼を持つ者が〈ひかり〉を見、音を軽やかに重ねつつ、なお危うげな足場を歩行する姿。そこにまた、
散る花と雪のあはひのゐなくなる
こうした句が現われ、動詞の働きにハッとさせられます。句の内容は消失感や無常観に傾くかもしれませんが、句の出だしに漢字三文字を用いた以外、ひらがなのみで構成する文字列に視覚的な明るさが感じられ、〈ゐなくなる〉の語調の小気味よさに宮本の魅力の一端を見ます。己を空しくした上での生への執着のなさ。かといって死に引き寄せられるのではなく。空しい己で消失を見据える視線の位置取りには、負の事象に寄り添いながらも自身を見失わない精神の芯を感じます。
ここからさらに句の世界は奥へと行きます。
三人とががんぼのゐる夜なりけり
と他者の存在が明示され、〈ゐる〉と記される生の記録。独り消えゆくのではなく、〈三人と(…)ゐる〉と書き得ること。〈ビール買ふ袋に伸びてゐるセロリー〉の〈セロリー〉にさえ他者性を感じうる生活の息づかい。〈月をゐて満月をゐてさみしがる〉では、〈ゐ〉る位置から〈さみし〉さを受け止める意志のさま。
ぽつねんと空うぐひすとすすむ沼
客観叙述を基調としながら〈ぽつねんと〉の語に心象がにじみます。〈空〉と鳥の取り合わせが見られるのは〈みづうみの〉の句と同様ですが、〈みづうみの〉の句に感じられる自由さや開放感とは異質なものが漂います。たやすくは姿を見せない〈うぐひす〉と〈すすむ〉道行きに添えられた〈ぽつねんと〉、〈沼〉の訥々とした語調には、ともすると初春の、暖かさへと至る手前の中途さのような、やや低調な心境を感じます。〈空〉、〈沼〉と二つの体言止めから生じるリズムには、見渡そうとしては止まり、それでも視線を上げて歩む足どりが感じられ、〈崖線を〉から続き、宮本が己の内面に何らかの敢えての意志を働かせて、自身を自身で支え進むさまが伝わってきます。
かうかうと氷に空がある拝む
〈氷〉の面に映る〈空〉を見たのでしょうか。〈拝む〉とは心を無にする所作であり、生の場所で死と向き合う行為といえます。己を空しくして句作する人が〈拝む〉と句に書くとき、生の位置から、なお向かい合う彼岸へ虚心に手を合わせる姿が浮かびます。生と死の端境に立つことを〈かうかうと〉と表わす心情は、自身を支える構えを以て、喪失をまばゆさのなかに見つめ、とらわれから離れつつ悲しみを抱える自由さを得ていくさまに思えます。己を空しくする句作の姿勢を保ちながら、生と死の〈あはひ〉に立ち、なお生の位置を把持する句が散見されるところに、私は第一詩集からの変化を感じます。
口中にひかる雲雀の落ちてくる
〈十月の〉の句にも見られる〈ひかり〉は、ここに至り〈口中にひかる雲雀〉となって〈落ちて〉きます。より身体に近く宮本の眼は幻視のように情景をとらえて心身の一致の下にあり、〈みづうみの〉の句へと続きます。
〈かうかうと〉の句に見る生の位置の確かさ、〈口中に〉の句に表わされた身体性を伴う幻視のイメージ、それらを経由して〈みづうみの〉の句が生まれていくかのようです。〈ひばりのなか〉が宮本にはありありと見えているのでしょう。身体性を伴って心象をまなざす眼を得、その眼に映る事物事象をも自己の身体感覚の延長で捉えるとき、客観叙述と心象表出の境界は薄れ、〈ひばりのなかに〉見つめる〈空〉は事物と心象の一致した場所で超然と〈空〉であるように感じます。換言すれば、自己の身体とも対象たる客体ともつかない自他の境ないまなざしによって、宮本が見出したものが〈空〉である自由さに、読み手の心まで解きほどかれるうれしさを覚えます。